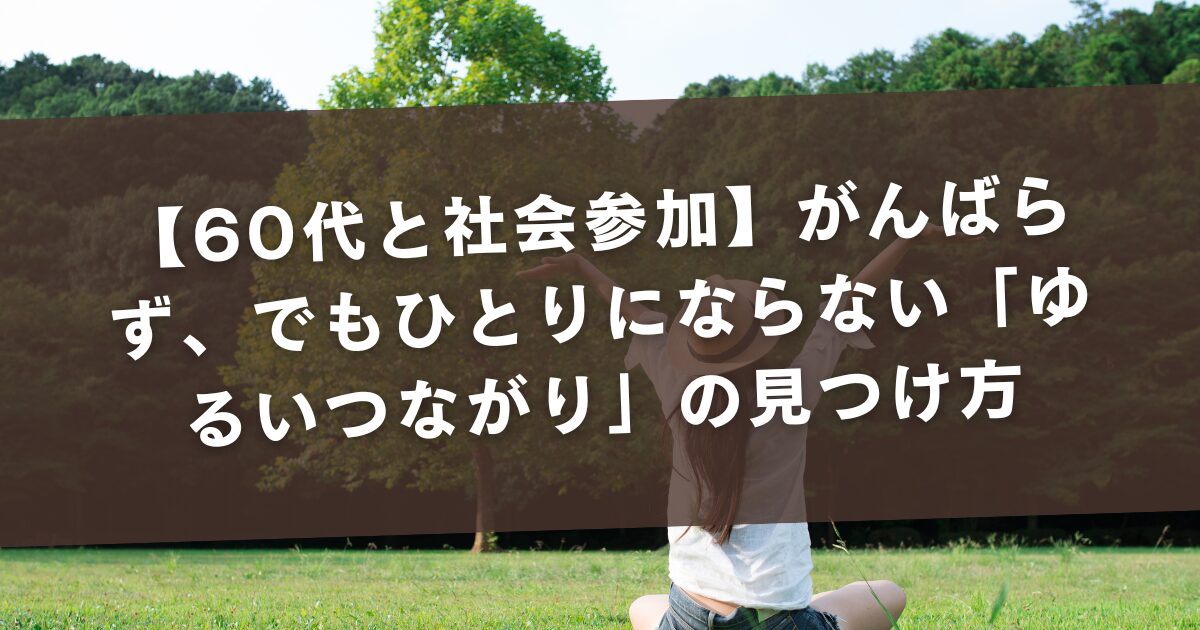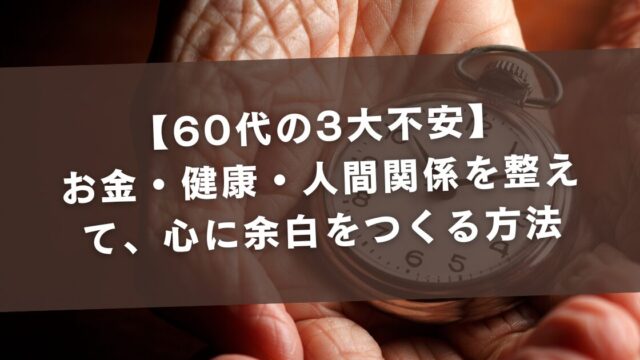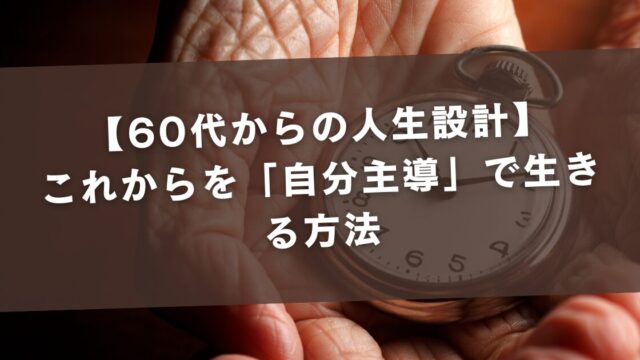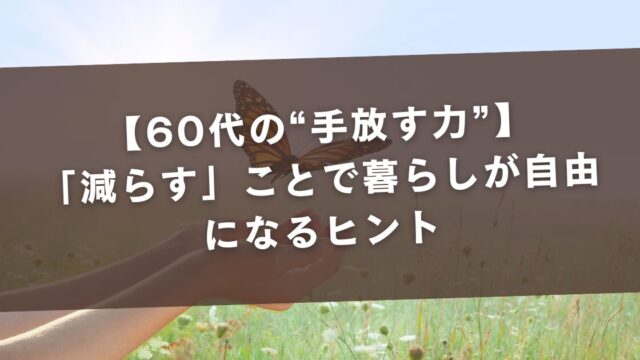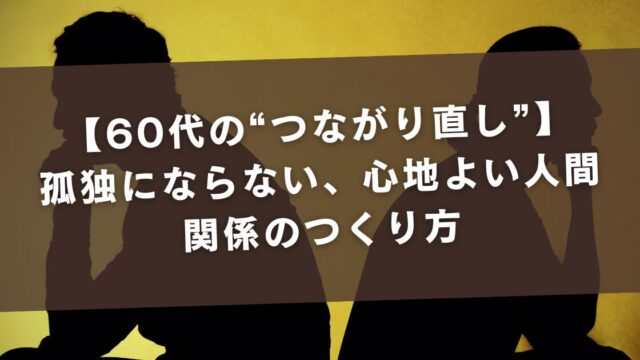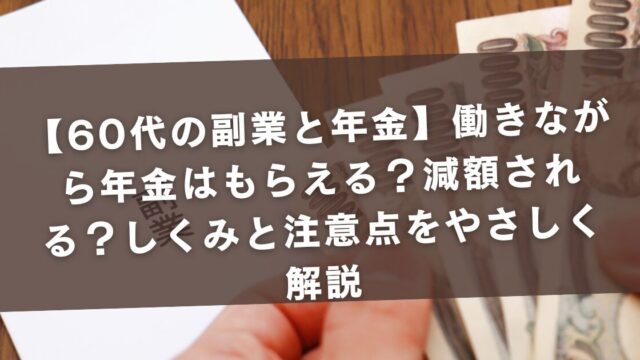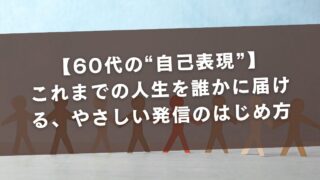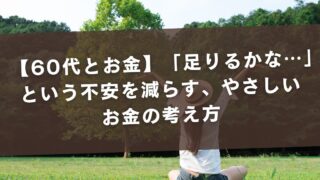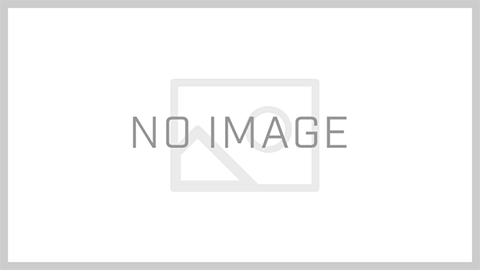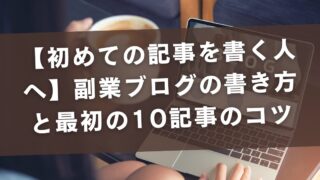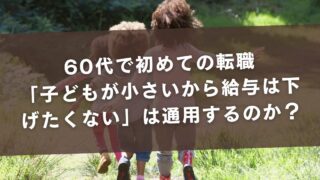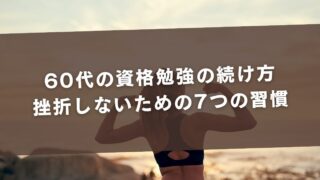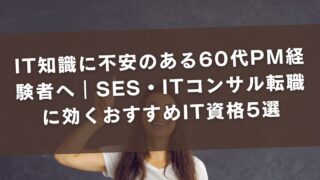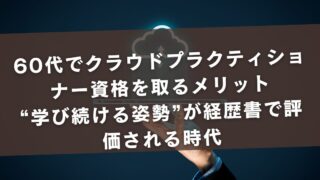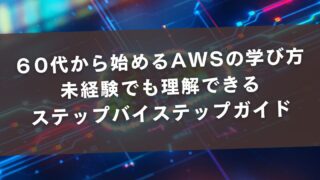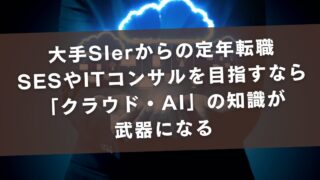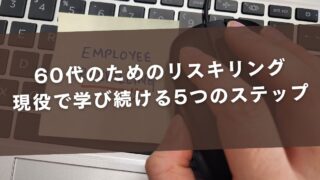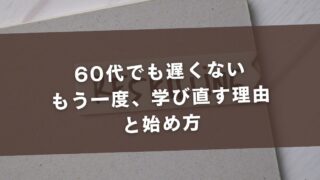「もう社会とは関係ない」なんて、思わなくていい
60代を迎えると、仕事から離れたり、役割がひと段落したりして、
社会とのつながりがふっと薄くなることがあります。
- 「もう誰の役にも立っていない気がする」
- 「誰とも会話せず1日が終わるのが不安」
- 「でも、無理に何かを始めるのもしんどい」
こんなふうに感じたことがあるなら、
それは“関わりたいけど、ちょうどいい形が分からない”だけかもしれません。
この記事では、60代からでも自然にできる、
“ゆるやかな社会参加”の方法と見つけ方をご紹介します。
なぜ60代に「つながり」は必要なのか?
人は年齢を重ねるほど、「孤立」のリスクが高まると言われています。
でも、関わり方次第で、それは防げます。
▷ 社会との“ゆるいつながり”がある人ほど、幸福度が高い
- 日々の会話の相手がいる
- 誰かに「おはよう」と言われる
- 自分を「知ってくれている人」が1人でもいる
こうした小さな関係が、心の安心感をつくってくれるのです。
【1】社会参加は「働くこと」じゃなくていい
社会参加=ボランティアや就労と考える方もいますが、実はもっと幅広いものです。
▷ 「少し関わる」「ちょっと顔を出す」だけでも十分
- 図書館や公民館でのワークショップに参加してみる
- 市民農園を見学してみる
- 朝のラジオ体操に「見るだけ」で行ってみる
大切なのは、「行ってみた」「覗いてみた」という行動そのもの。
関わりの形に“正解”はありません。
【2】ゆるやかなつながりが見つかる5つの場所
① 地域の掲示板・市報・図書館
- 月1の読書会
- 映画上映会
- 手芸・歴史・俳句などのクラブ
「参加しなくても、雰囲気を見るだけ」で十分。
まずは“情報に触れる”ことから始めてみましょう。
② ボランティアセンターの“スポット参加型”活動
- 子ども食堂の手伝い
- 街の清掃活動(月1回)
- 孤立しがちな高齢者への手紙書き
※「週1以上の継続ボランティア」ではなく、単発で関われるものを選ぶと気が楽です。
③ オンラインでのゆるいつながり
- シニア向けZoom講座
- LINEオープンチャットの読書グループ
- noteやXで、同年代の発信者を見つけて“読むだけ”参加
リアルで疲れたら、“見るだけ”でも安心できる場所があると違います。
④ 自分が“できること”を小さく人に役立てる
- 近所の子に数学を教える
- 得意な料理を知人にふるまう
- スマホの操作で困っている人に声をかける
報酬がなくても「ありがとう」と言われる体験は、
自分の存在価値をそっと肯定してくれます。
⑤ 「居場所」より「気配がある場所」を持つ
- 行きつけの喫茶店で毎週同じ席に座る
- 朝の散歩コースで顔を合わせる人と軽く会釈する
- 家の前で掃除している人に「こんにちは」と声をかける
“話さないけれど存在を感じられる関係”も、立派な社会参加です。
【3】無理しない社会参加をする3つのマイルール
▷ ① “疲れたらやめる”を前提にする
気乗りしない日は無理に出かけない。
“継続しないと意味がない”なんて思わなくていいのです。
▷ ② 「知り合いができなくてもOK」にしておく
人間関係を築くことが目的ではなく、
「誰かの中に自分がいる時間を持つこと」が大切。
▷ ③ 「役に立つこと」より「心が動いたこと」を選ぶ
- 好きな本に関する集まり
- ずっと気になっていた音楽講座
- 植物を育てる小さなサークル
“役に立とうとしすぎると苦しくなる”のは、60代以降のよくある落とし穴です。
まとめ|あなたの“存在”が、もう社会とのつながり
社会参加は、何か大きな活動をしなければいけないわけではありません。
- 1時間だけ誰かと話す
- 誰かの役にちょっと立てた
- 知らない人と「こんにちは」と言い合った
それだけで、あなたはもう立派に“つながっている”のです。
「ひとりじゃない」と感じられる場所を、どうか焦らず見つけてください。
あなたが心地よくいられる社会との距離は、きっとあります。